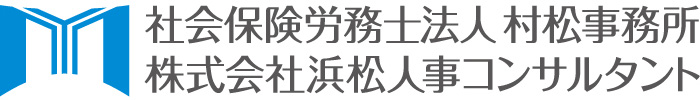お役立ち情報・BLOG
労務管理を学ぶ【法改正編📚】 育児介護休業法 柔軟な働き方を実現するための措置
いつも『労務管理を会話で学ぶ 🤔』をご覧いただきありがとうございます。
このブログでは、対話形式で労務管理のポイントをわかりやすくお届けしてきました💻
さらに情報の幅を広げるため、「法改正」「労務に関する最新トピック」「実務に役立つ豆知識」などを会話形式以外でも発信していきます。
今後は「労務管理を学ぶ」とタイトルを改めますが、人事労務に役立つ情報を、タイムリーかつわかりやすくお伝えしていきますので、ぜひ引き続きご覧ください😊
◆柔軟な働き方の実現とは?
2025年10月1日から育児・介護休業法の改正により、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員への「柔軟な働き方を実現するための措置」が企業に義務づけられます📗
具体的には、以下の①~⑤の選択肢の中から、2つ以上の制度を選択して導入し、対象となる従業員がその中から1つを利用できるようにすることが必要になります。
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置・運営等
④養育両立支援休暇の付与
⑤短時間勤務制度
◆企業の実際の対応状況は?
労務行政研究所による調査(2025年4月実施)では、「既に措置を実施している」が55.2%、「実施する措置が決定しており、今後実施予定」が16.6%と、約7割の企業で対応が決定していました。
選択した措置の内容については、「①始業時刻等の変更」と「⑤短時間勤務制度」を選択した企業が43.4%と最多でした。
また、「①始業時刻等の変更」と「②テレワーク等」と「⑤短時間勤務制度」の三つの措置を導入している企業も24.7%と続き、これら上位2パターンで約7割を占めています。
村松事務所へも多くの相談がありますが、「①始業時刻等の変更」と「⑤短時間勤務制度」を選ぶ企業が特に多い傾向があります。
◆働く母親の割合が過去最高に
厚生労働省の2024年の国民生活基礎調査の結果を見てみると、2024年時点で児童のいる世帯における母親の就業率は80.9%と過去最高を記録しました👩👧👦
正規雇用の割合も年々増加しており、2004年で16.9%→2024年では34.1% となっていて、正社員で働く母親の割合が倍増しています⤴️⤴️
このような状況からも、子を養育する従業員への「柔軟な働き方を実現する措置」がますます重要であることが明確です。
◆今後の対応について
企業の制度にあった「柔軟な働き方を実現するための措置」を選択し、その内容については従業員の過半数代表者等の意見を聴取する機会を設ける必要があります。
また、就業規則(育児・介護休業規程)等の見直しも求められます。
従業員が働きやすい環境を整備し、子育て世代の活躍を後押しすることは、企業の人材確保・定着に関わる重要な施策です❗
村松事務所にも「柔軟な働き方を実現するための制度導入」や「就業規則(育児・介護休業規程)の見直し」に関するご相談が増えています。
法改正への対応はもちろんですが、特に中小企業においては自社の実情にあわせた制度設計が求められます。
対応にお困りの際は、お気軽に村松事務所へご相談ください☎️

■参考サイト
厚生労働省 「育児・介護休業法改正のポイント」
一般財団法人労務行政研究所「改正育児・介護休業法への対応アンケート(2025年4月、10月施行)」
厚生労働省 「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」